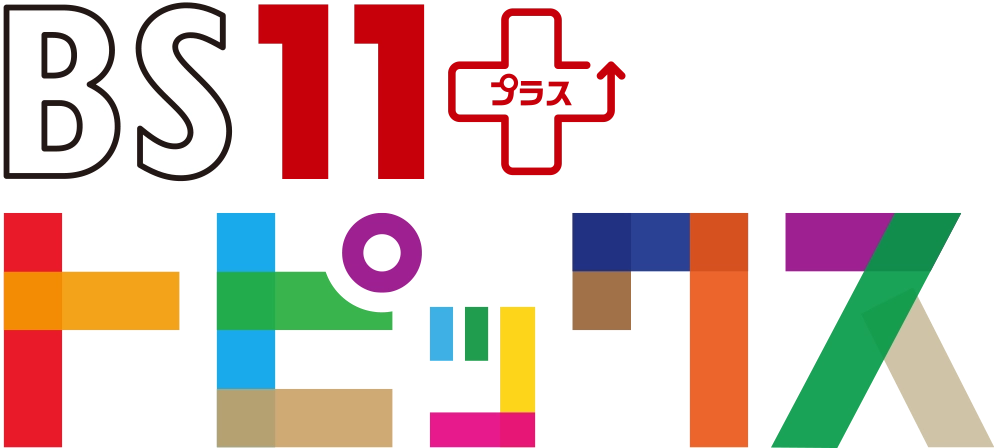第53回は、戦国時代きっての個性派、前田慶次を取り上げました。傾奇者(かぶきもの)として名高い彼の華やかな生き様の裏には、意外にも深い挫折と選択の物語がありました。
家督を奪われた“敗北”がすべての始まりだった

前田慶次については資料がとても少ないのですが、一説によると1541年頃、尾張に生まれたとされています。前田家の養子として跡継ぎの道を歩んでいたのですが、織田信長の命により、家督は叔父・前田利家へと譲られます。このとき慶次は「武家のエリートコース」から転落。以後、転々とする流浪の日々が始まります。 一時は前田家に戻り、城代として活躍しますが、利家の出世と対照的に自らの存在意義を見失っていきます。利家の忠義一辺倒の姿勢や、秀吉にすり寄る処世術に反発し「自分の居場所はここにはない」と感じた慶次は、ある日を機に前田家を去ります。自ら「敗北」の道を選んだその姿は、まさに傾奇者としての決意でした。
自由人・慶次、文化の都で新たな道を拓く

出奔後の慶次は、京都で茶の湯や連歌などの文化に触れ、文人としての素養を深めていきます。特に千利休の後継者・古田織部に師事したという逸話もあり、ただの変わり者ではなかったことがうかがえます。

この頃、学問好きの名将・直江兼続と出会い、意気投合。上杉家の家臣として仕えることとなります。関ヶ原の戦いでは「北の関ヶ原」と呼ばれる出羽の戦に出陣し、撤退する上杉軍の殿(しんがり)をみごと勤め上げました。
戦に敗れた上杉家が米沢に転封された後も、慶次は新天地に同行します。そこで過ごした晩年は、「自由人」としての集大成でした。
天下人・秀吉も思わず笑った、傾奇者の才知
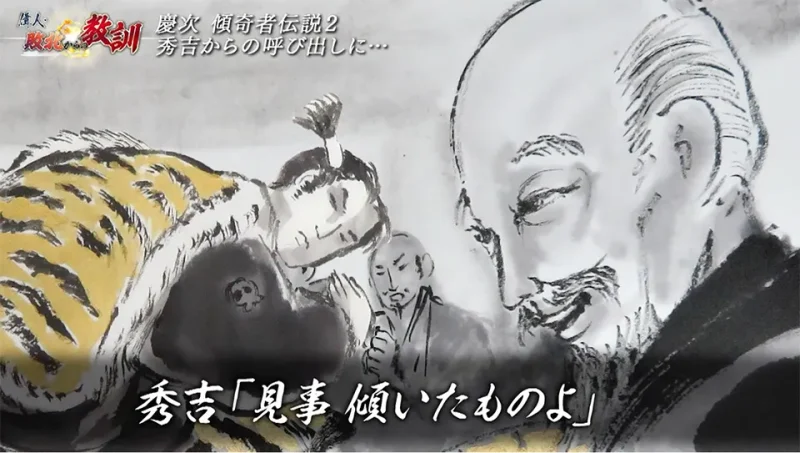
その自由さは、時の権力者・豊臣秀吉との対面でも発揮されました。秀吉に召し出された慶次は、正面から頭を下げるのを良しとせず、「横を向いてお辞儀をする」という奇策に出ます。これには周囲の大名たちも肝を冷やしましたが、沈黙を破ったのは秀吉の笑い声。「見事にかぶいたものよ」と感嘆し、慶次に馬を褒美として与えたといいます。慶次はさらに正装に着替えて再び秀吉の前に現れ、礼法に則った美しい所作で魅せました。型破りでありながらも、礼節をわきまえた振る舞いは、まさに傾奇者の真骨頂でした。
書き残した道中日記と、謎多き最期
慶次が米沢へ向かう道中を記した『前田慶次道中日記』には、和歌や風俗、噂話などが記されており、彼の文学的素養とユーモアに満ちた感性が伝わってきます。戦国の武将というよりは、文化人としての顔が強く浮かび上がる貴重な記録です。

慶次が没したとされる米沢市には、力石や月見の宴が伝わる場所、墓所とされる地も残っており、村人との交流も深かったようです。慶次は「生きるだけ生きたのは、死ぬでもあろうか」という言葉を残してこの世を去ったと伝えられています。
伊東潤が見る「もう一つの慶次」
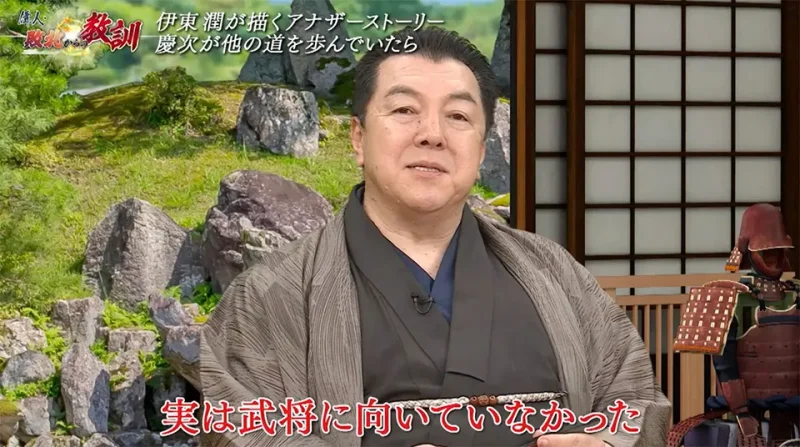
歴史作家の伊東潤先生は「慶次は武将に向いていなかった」と語ります。むしろ茶人や文化人として生きていれば、新たな茶の流派を創出していたかもしれません。慶次は高い自己肯定感を持ちながらも、出世には結びつかず、不遇と挫折を抱えていました。それでも自らの美学を貫き、自分らしく生きた姿には、現代にも通じる誇り高き敗北の教訓があるといえるでしょう。
「前田慶次・出奔を選んだ天下御免の傾奇者」まとめ
武将として大成することはなかった前田慶次。しかし、文化人としての才能、そして何より自分を貫く強さが、今も人々の心を惹きつけてやみません。紹介しきれなかった内容は、ぜひ番組をご視聴ください!