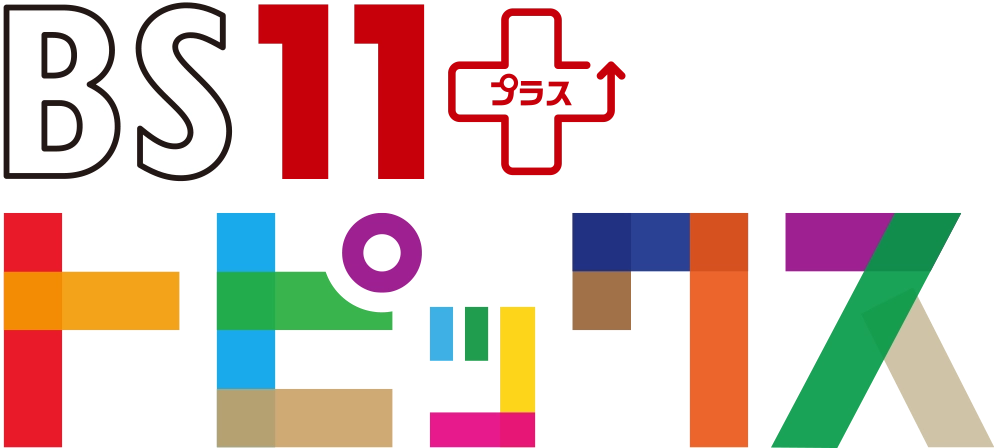秀吉に敗れた武将たちに焦点を当て、現代に通じる教訓を見つけていく「シリーズ秀吉」。第1弾は、中国地方の大名・毛利輝元です。秀吉と挑んだ備中高松城の戦いにおいて、毛利輝元はなぜ不利な条件で講和を選択せざるを得なかったのでしょうか。
輝元の育った背景

毛利軍は中国地方の大名として広大な領土を持ち、その存続を最優先とする姿勢が強かったため、決断力に欠ける傾向がありました。伊東潤先生は「毛利輝元は、祖父・毛利元就と叔父たちに支えられて育った影響から、自らの判断で大胆な行動を起こすことが難しかった」と説明します。

当時、毛利家は織田家と同盟関係にありましたが、信長が西国への勢力拡大を図る中で緊張が高まり、信長は毛利家攻略を豊臣秀吉に命じます。

秀吉は備中高松城で輝元と対峙。この城は広大な低地地帯の中に築かれた平城で、周囲の沼地が天然の堀を形成する難攻不落の城でした。秀吉は、堤防を築き川の水を引き込むという大規模な水攻めを行います。ついに輝元は停戦を決断し、城主・清水宗治の切腹を受け入れることで和睦が成立します。
なぜ輝元は敗北したのか

秀吉は中国地方攻略のため、備中の国に7つの城から成る境目七城を攻略していきました。毛利家内部の調略にも力を入れ、輝元の身内である領主たちを次々と寝返らせることで、毛利軍の結束を崩していきます。
戦況の転換点となったのは、織田信長が明智光秀の謀反により本能寺の変で討たれたことです。秀吉はこの情報を察知すると、毛利軍に悟られないよう迅速に停戦交渉を進め、輝元に不利な条件を飲ませることに成功しました。こうして毛利家は事実上、秀吉に敗北を喫したのです。
輝元が勝てるチャンスはなかったのか
毛利が勝てるチャンスはなかったのでしょうか。例えば荒木村重が寝返ったときになどに輝元が積極的に上洛を目指していれば、戦局は異なっていたかもしれません。伊東潤先生は、輝元の敗北について「優柔不断な姿勢が組織全体に悪影響を与えた」と分析しています。大名として領土を守ることを最優先にした結果、機を逃し、結局は厳しい選択を迫られることになりました。

一方、織田軍は信長の強力な経済基盤と組織的な統制、秀吉の調略や迅速な行動によって多くの敵を味方に引き込むことに成功しています。
この戦いから学べる教訓として、決断のタイミングの重要性が挙げられます。戦局を見極め、時にはリスクを冒してでも積極的に行動することが、組織の存続にとって不可欠であることが示されました。また、部下の忠誠心を維持するためには、指導者自身が明確なビジョンを持ち、迅速な判断を下すことが求められるのです。
シリーズ秀吉①高松城水攻めと毛利輝元まとめ
備中高松城の戦いは、組織運営やリーダーシップの教訓を現代に伝えてくれています。毛利輝元の慎重さと秀吉の迅速な判断の対比から、指導者としての資質がいかに戦局を左右するかを学ぶことが出来ます。詳しくはぜひ番組をご覧ください。