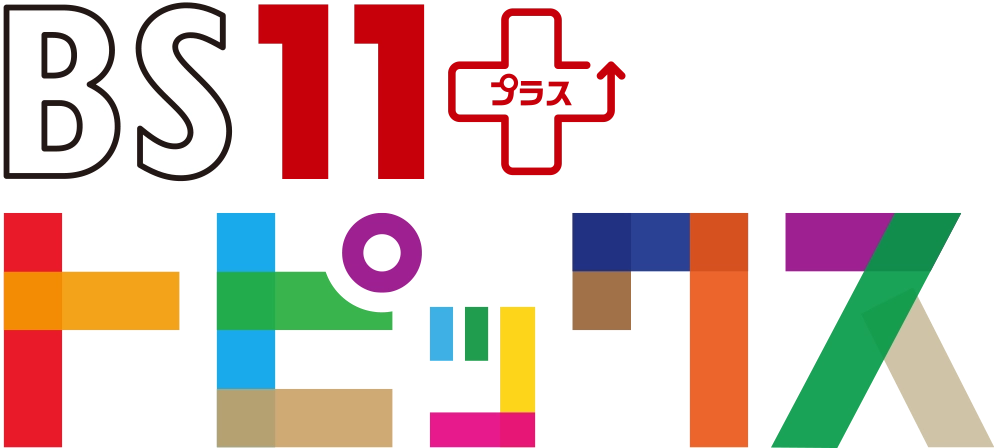千年以上の歴史を誇る京都・祇園祭。その華やかさを象徴する山鉾巡行の陰で、厳かに、そして力強く執り行われているのが「神幸祭」と「還幸祭」です。この祭りの真髄とも言える神輿渡御において、神を先導し、命懸けで奉仕を続ける男たちがいます。八坂神社の氏子組織「宮本組」について紹介します。
神を先導する宮本組の使命

宮本組は、八坂神社の氏子組織「清々講社(せいせいこうしゃ)」の中でも筆頭格にあたる存在です。神社を含む祇園町のお膝元として、明治以前から祭礼に奉仕してきました。中でも重要なのが、神幸祭・還幸祭における御神輿の先導役です。神の“お宝”とされる六種の御神宝(御神鏡・玉・剣・琴など)を担ぎ、神輿の先頭に立つその役目は、宮本組にしか許されていません。
厳粛な準備と、御神宝を担う誇り

祇園祭は7月の一カ月間に渡って行われます。7月1日の山鉾町吉符入り、籤取式、稚児舞披露など、一つ一つの儀式が行われるたび、京都の町が祇園祭に染まっていきます。

祭りの幕開けを告げる「神輿洗」は7月10日と28日に行われます。鴨川から汲み上げた聖なる水で神輿を清めるこの神事も、宮本組の大切な務めです。神輿の前を照らす大松明を担ぎ、境内から出発するその姿を見ていると、次第に祇園祭本番への期待が高まっていきます。
熱気と祈りに包まれる神輿渡御

神幸祭当日。夕刻、八坂神社から三基の神輿が練り出されると、町は熱気に包まれます。総勢二千人もの輿丁が担ぐ神輿は、豪快に「差し上げ」「差し回し」といった動きを見せ、観客の歓声と拍手が響き渡ります。その最前列を進むのが、御神宝を高々と掲げる宮本組。神の力を最大限に引き出し、疫病を鎮め、町を清める。その使命に込められた想いは、千年を超えて受け継がれてきたのです。

神輿がたどり着くのは四条寺町にある「御旅所」。神様はここで1週間を過ごし、町の人々に静かに寄り添います。その間も宮本組の役目は終わりません。御神宝の展示や飾り付け、神事への奉仕は続きます。そして24日の還幸祭。再び町を練り歩いた神輿は、八坂神社へと戻ります。長く熱い夏の一幕が厳かに幕を閉じるのです。
祇園祭まとめ:受け継がれる祈りのバトン
常盤さんは「千年前の祈りを千年先に繋ぐために奉仕しているという気持ちが伝わってきた」と感動の様子。宮本組の人々が語った「趣味や楽しみではなく、祈りの気持ちを受け継ぐ中継役として奉仕している」という言葉が、祇園祭の本質を教えてくれました。紹介しきれなかった神事の様子は、ぜひ番組をご視聴ください!